筆録(20) 石を抱いて実腹せよ(抱石大人名説)
実腹法とは、先師・曲全坊老師が、ご自身の仙道修行の要諦を一呼吸法に凝縮され、老子道徳経第三章「虚心実腹」の語句から「実腹法」と名付けられた丹田呼吸法である。
実腹法と曲全坊老子については、いずれこの筆録で詳しく述べねばなるまい。
名説(めいせつ)とは、筆者の造語であって、古典にはない。人の名には、その人のみたま振りが表れる。従って、「名の説明」は、その人のみたま振りの説明となる。
若い頃にかなりの数の名説を書いたのだが、散失して手元に残るのはこの「抱石大人名説」のみである。ここに採録して亡失を防ぐ。(平成22年8月6日)
下士は大脳智を巡らせるのみ
人からものを頼まれて、「考えておこう」と答えるのは往々にして婉曲な断りとなる。
「考えておこう」と言いながら、本当にそのことを考える人は少ない。
仮に大脳智をめぐらせてあれこれと考えてみたところで、三界に新たな悪因を打ち立ててやがて悪果を刈り取る外は無い。
大脳智にのみ依拠する者は、下士と云わざるを得ない。
中士はキョウ気の世界に輪廻を繰り返す
中士は、胸を叩いて「引き受けた」と請け負う。
「人を恋うる歌」
妻をめとらば才たけて
みめ美わしく情ある
友をえらばば書を読みて
六分の侠気四分の熱 (中略)
あゝわれダンテの奇才なく
バイロンハイネの熱なきも
石を抱きて野にうたう
芭蕉のさびをよろこばず
胸は共感の出づる場であるので、世人はこの中士を以て肝胆相照らす友と為し、あるいは真の侠客と為す。
「六部の侠気、四部の熱」とは蓋し中士の信条を正に述懐(懐を述べる)したものである。
しかし、侠気は、時に狂気となり凶器を振るうの挙に出でることがあるのは、未だ堂奥に入り得ていないからである。即ち、「六分の侠気」の心根は未だ相対世界に在って分別感を脱却し得ず、「四分の熱」を激らせて競争に狂奔する。
勝っては強者として騎慢を誇り、負けては恐怖して怯儒に陥る。強弱勝敗は共に天地の大道から見れば、狭路を歩む凶相である。
中士とは、中等を意味するのではなく、その実態は未だキョウ(胸、共、侠、競、狂、強、騎、恐、怯、狭、凶)気の世界に輪廻を繰り返す小人と言わねばならない。
上士は、大脳智を空しくして丹田に気を鎮める
上士とは、大脳智を空しくして(虚心)、丹田に気を鎮め(実腹)、天地と共に無為の大道を歩む人をいう。
頭に気が上ってハーハーと肩で息をするのは論外であるが、胸をせかつかせての胸式呼吸も、真玄の気が未だ胴奥(丹田)に達せず、落ち着きが得られない。
肝胆相照らすは未だ俗客の交わりに過ぎず、肝胆の更に奥深く丹田に真気が充ちるのでなければ、真人仙客の友とは成り難い。
石を抱いて実腹せよ
東海の親友白井善夫君が地元の朋友と相図り、実腹法の研鐙に志したことは、大慶の至りである。
白井君も漸くにしてキョウ気の世界から一歩を脱して「石を抱いて野に歌う芭蕪のさびを喜」ぶの境地に踏み入る心が兆したと言えよう。
石を抱くならば、大石を抱くがよい。
大石を懐に抱けば、到底懐(肝胆)に安住し得ず丹田に落ちざるを得ない。
真玄の気を丹田に収めるの要諦は、あたかも大石を抱くが如しである。鼻孔より吸い込んだ気を大石と化して丹田にぷち込めば、虚心実腹(老子第三章)の相は自ずから或る
。
かくして初めて、大脳智の跳梁を鎮めて相対分別観を脱却し、腹脳を開いて絶対界に心根を置く全一観の上士となる。即ち、無為の大道を歩む大人となる。
よって今後は白井善夫君を抱石大人と尊称し、東天を仰いで大人の真我を礼拝する。
石を抱いて、実腹せよ!
(平成三年四月九日、実腹法の解説を求められて筆を進めるうちに抱石大人の命名と名説を得た。大入御本体の益々の発現を祈る。襲明道人)


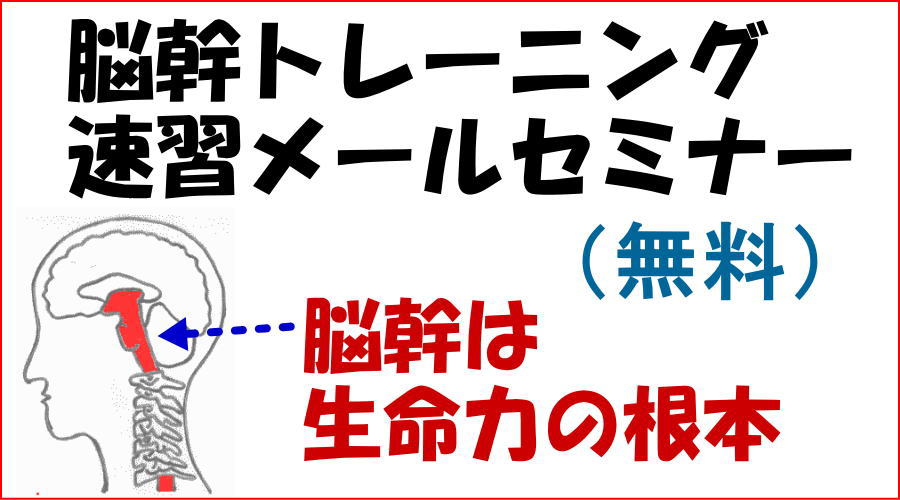


 /
20歳から科学技術翻訳士として技術翻訳の世界に入り、以後プロ翻訳数十年。神道を行じつつ、日本語と英語の構造の違いに悩まされた結果
/
20歳から科学技術翻訳士として技術翻訳の世界に入り、以後プロ翻訳数十年。神道を行じつつ、日本語と英語の構造の違いに悩まされた結果