億劫(おっくう)と科学技術の進歩
「億劫(おっくう)」という言葉がある。科学技術の進歩とどういう関係があるのか、怪訝に思われるかも知れません。
実は関係大ありです。というよりも、力尽くで関係をこじつけて見せましょう。あはは。
億劫(おっくう)とは、億劫(おくこう)から
「億劫(おっくう)」という言葉は、元は「億劫(おくこう)」と読んだはずです。一つ二つと劫(こう)を重ねて、ついに億劫(おくごう)にまで達する。それは気の遠くなるような長い時間を表す言葉でした。
「劫(こう)」というのは、インド哲学から仏教に流れ込んだ言葉で、とても長い時間の単位を表します。どれほど長いのかと申しますと、百年に一度、空から天女が舞い降りてきて、一辺が四十里もある大きな岩を、透き通るような羽衣で一度撫でる、それを繰り返して大岩がすり切れてなくなるまでの時間が、一劫であるというのです。(仏典『大智度論』)
一劫ですら、気が遠くなるほどの長い時間ですが、億劫となると、もう人間の意識の範疇を超えて、宇宙論的な時間と言わざるを得ません。それほどの長い時間をかけて何かを成し遂げようとすると、いかに意志強固な人間であっても、「億劫(おっくう)」にならざるを得ません。「億劫(おくこう)」が「億劫(おっくう)」に変化したのは、そういうわけです。
塵劫記の塵劫(じんこう)とは
先の記事「数字の名前、億、兆、京、その次は?」において、『塵劫記(じんこうき)』に記載の、気の遠くなる程大きな数字の単位について述べました。
『塵劫記(じんこうき)』の書名になった「塵劫」自体が、とても大きな時間を意味する言葉です。
それは法華経の「塵点劫」から採った言葉であり、「塵点劫」とは、「この世の土を細かく砕いて粉にしたものを千の国を通るたびに一粒ずつ落としていき、その砂がなくなるまでに通る国の数のことで、数えきれないくらい大きな数のたとえ」とか。(Wikipedia 「塵点劫」)
『塵劫記』の作者・吉田光由は、人間の意識の極限を超えると思われる数字の世界に、想いを致そうとして『塵劫記』という書名を思いついたのでしょう。塵劫にしろ、億劫(おくこう)にしろ、これほど大きな数字を思い浮かべると、人生の些細なことに悩む人間が馬鹿らしくなってきますね。
億劫(おっくう)と科学技術の進歩
さて、億劫(おっくう)と科学技術の進歩について述べねばなりません。
科学技術の進歩というものは、多くの科学者の血のにじむような研究の繰り返し、実験の繰り返しによってもたらされるものであります。
研究者が、研究実験を重ねて一つの発見にいたるまでには、どれほどの繰り返しが必要であったことか。しかも、いつまでやれば成果が出るという見通しは全くないのです。
何月何日までと期限を明示されたら、人間は何とかその日まで持ちこたえられるのですが、どこまでやれば成果がでるのかが分からないという状況で、研究実験を続けるというのは、とても強烈な意志力が必要です。
未踏の分野で新しい発見にいたるためには、前途に「億劫(おくこう)」の道を覚悟しなければなりません。前途の「億劫(おくこう)」の道にたじろいで、「億劫(おっくう)」になどなってはいられません。
科学者が、時に学問の歴史を塗り替えるような大発見を成し遂げることがありますが、それはすべて「億劫(おくこう)」の道に「億劫(おっくう)」にならずに立ち向かったからであります。
科学技術の進歩というものは、「億劫(おくこう)」の道に「億劫(おっくう)」にならずに立ち向かって来た科学者や技術者によってもたらされたものです。
「億劫(おくこう)」の道に「億劫(おっくう)」にならずに立ち向かうには、強固な信念が必要です。
ケプラーが、ティコ・ブラーエの残した膨大な天体観測データから、コンピュータのない時代に手計算でデータを整理して、ケプラーの法則という美しい形式を見つけ出したのは、彼らのキリスト教世界観の賜物でした。
つまり、神が造り給うたこの世界には、美しい法則が存在するはずだという揺るぎがたい信念があったが故に、膨大なデータの計算、計算、計算を何年も何年も繰り返して、とうとうケプラーの法則に至ることができたのです。
これもまた、「億劫(おくこう)」の道に「億劫(おっくう)」にならずに立ち向かった研究者が成し遂げた成果の一例です。
何月何日まで頑張れば成果が出るという保証がまったくない「億劫(おくこう)」の道に「億劫(おっくう)」にならずに立ち向かったからです。
子供たちがよく尋ねます。「この作業、いつまでやればよいの?」
それに対して「いついつまで」と答えてはなりません。
正しい答えは、「出来るまで頑張りなさい」ということですね。


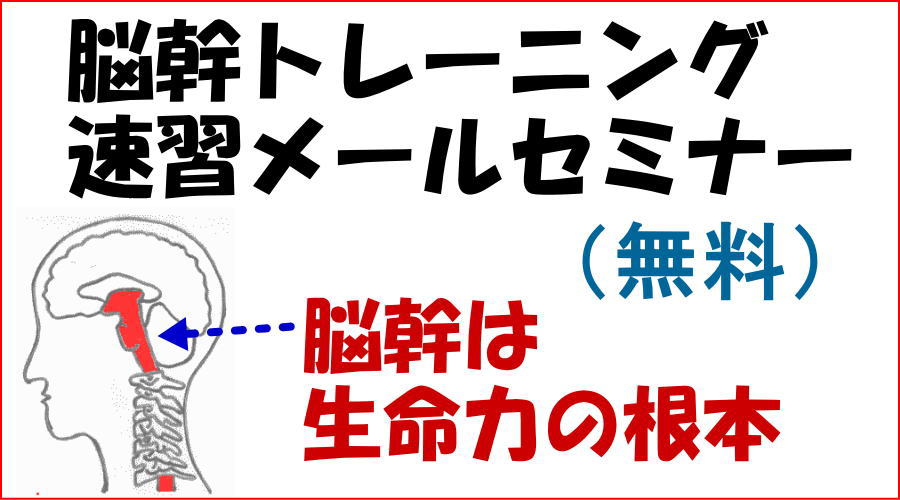

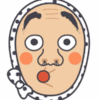

 /
20歳から科学技術翻訳士として技術翻訳の世界に入り、以後プロ翻訳数十年。神道を行じつつ、日本語と英語の構造の違いに悩まされた結果
/
20歳から科学技術翻訳士として技術翻訳の世界に入り、以後プロ翻訳数十年。神道を行じつつ、日本語と英語の構造の違いに悩まされた結果